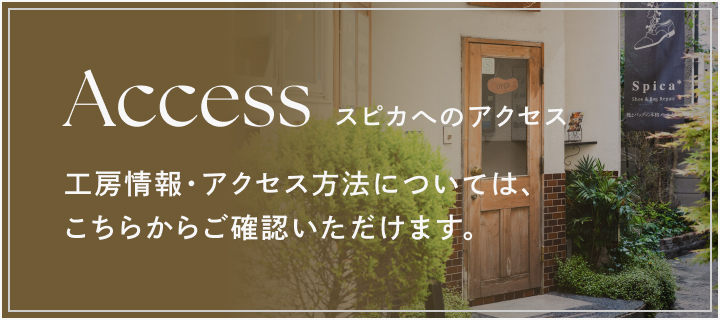「革靴はメンテナンスが必須!」と聞くけど、いざ革靴を買ったら何から手をつけていいのかわからない…、という方も多いと思います。
そこで本記事では、具体的にどう革靴をメンテナンスしていけばいいのか?を革靴職人が徹底解説していきます!
この記事を読めば、こんな悩みが解決します!
- そもそも「革靴のメンテナンス」って何するの?
- 揃えるべき必需品は?
- 履いた「その日」にすべきメンテナンス
- 数ヶ月に1度行う「スペシャルケア」のやり方
そもそも「革靴のメンテナンス」って?
革靴メンテナンスの基本とは?

革靴のメンテナンスとは、単に靴をきれいに見せるためだけでなく、革自体の寿命をできる限り延ばすために欠かせない習慣です。
革は天然素材であり、時間の経過とともに乾燥や摩耗が進みます。そのまま放置するとひび割れや型崩れが起きやすく、せっかくの高級靴も見た目が損なわれてしまいます。メンテナンスを定期的に行うことで、革の艶や風合いが蘇り、履き込むほど足に馴染む魅力を保ち続けられるのです。
また、見た目だけでなく、清潔さや快適さを維持するためにも効果があります。
汗や汚れをきちんと落とすことは、雑菌の繁殖を防ぎ臭いの軽減にもつながるため、足元から清潔感を演出できます!
なぜメンテナンスが必要なのか?
革靴はスニーカーと違い、消耗品というより「使いながら育てる道具」に近い存在です。そのため、購入時が一番きれいな状態ではなく、手をかけて履くことで徐々に深みが増していきます。
革は呼吸している素材のため、乾燥や湿気の影響を強く受けます。
定期的にクリームで油分や水分を補わないと硬化し、ひび割れや色あせを招きますし、雨や泥汚れもシミの原因となるため、適切なケアが必要なのです。
さらにソールやかかとなどは摩耗が避けられない箇所ですが、早めの修理や交換を行えば靴全体を長持ちさせることができます。
【まずは揃えよう!】メンテナンス用のシューケア用品
革靴を長く美しく履き続けるためには、正しいシューケア用品を揃えることが必要。ここでは基本的な用品を紹介し、それぞれの役割と必要性を解説します!
馬毛ブラシ ― ホコリ落としの必需品
一番最初に用意したいのが「馬毛ブラシ」です。
柔らかい毛質で革を傷つけにくく、日常的に軽くブラッシングするだけでホコリや細かな汚れを落とせます。革靴は外を歩くことで細かい埃や砂が付着しますが、これを放置すると革の表面にダメージを与え、ひび割れや劣化の原因になります。
馬毛ブラシで習慣的に掃き落とすだけで、後のクリームやワックスの浸透もスムーズになり、全体的なメンテナンス効果が高まります。
豚毛ブラシ ― クリームの馴染ませ役
次に必須となるのが「豚毛ブラシ」です。
馬毛ブラシに比べて硬さがあり、革靴クリームを塗布した後に使用すると、クリームがしっかりと革の繊維に浸透し、表面のムラを整えます。
艶を引き出す仕上げの段階でも活躍するため、一本持っておくと非常に便利です。ブラッシングによって余分なクリームが除去されることで通気性も保たれ、革の呼吸を妨げないのが大きなメリットです。
余裕があれば「ヤギ毛ブラシ」もあるとGood!
なかなか聞きなれないかもしれませんが、ヤギ毛ブラシというものもあります。
使用用途は鏡面磨きなどの後に、よりツヤや光沢を出すためにクリームを均す用途で使われます。
ただし「毎日のメンテナンスに不可欠!」というわけではなく、鏡面磨きや複数靴をより丁寧に磨きたい時にあると便利な用品ですので、必ず必要というわけではありません。もし靴磨きになれてきて、より丁寧に磨いてみたい!という方は購入を検討いただけるといいと思います!
靴クリーム ― 栄養と色艶を与える必需品
靴クリームは革靴に命を吹き込むアイテムといえます。乳化性クリームは油分と水分を補給し、革の柔軟性を保ちながら自然な艶を出します。
色付きのクリームを選べば、擦れや色あせた部分を補色でき、見た目をぐっと引き締める効果も得られます。これを怠ると革は乾燥し、パサついたり皺が深く刻まれる原因になります。どんなに高級な靴でもクリームなしでは劣化は避けられないため、必ず揃えておきたい基本用品です。
クロス ― 汚れ取りから仕上げまで
柔らかい布、通称「クロス」も欠かせないケア用品です。まずは汚れや古いクリームを拭き取る用途に使え、次に新しいクリームを塗る際のアプリケーターとして活躍します。
さらに仕上げの磨き上げでは余分な油分を吸収しながら革に艶をもたらします。Tシャツの古布でも代用できますが、できれば起毛がなく滑らかな綿素材を用意すると、ムラなく美しい仕上がりになります。
シューツリー ― 型崩れ防止のパートナー
最後に紹介するのは「シューツリー」です。
見落とされがちですが、実は最も重要なケア用品のひとつです。靴を脱いだ直後に入れることで、湿気を吸収しつつシワを伸ばし、革の型崩れを防ぎます。特に木製のシューツリーは調湿効果が高く、靴内部の環境を良好に保ちます。
「履いたその日」のメンテナンス

革靴は一日履くだけで、汗やホコリ、歩行によるシワなど様々な負荷がかかっています。
そのため「履いたその日」に行う簡単なケアこそ、寿命を大きく左右する基本習慣となります。ここでは毎日実践すべきメンテナンス方法を紹介します!
革靴の寿命を大きく左右するのは、実は「履いたその日の過ごし方」です。一日履いた靴は汗やホコリを吸い込み、負担が蓄積しています。そこで、帰宅直後から翌日までの流れを時系列で整理してみましょう!
①:帰宅直後 ― 馬毛ブラシでホコリを払う!
玄関に戻ったら、まず馬毛ブラシで全体を軽くブラッシングします。
表面に付着したホコリや砂粒をその日のうちに落とすことで、革の表面が削られたり乾燥してひび割れるリスクを防げます。特にソールの縫い目や靴のコバ周りには細かいゴミが溜まりやすいため、丁寧に掃くのがポイントです。
②:靴を脱いだら ― シューツリーを装着して形を整える!
ブラッシングを終えたら、すぐにシューツリーを入れましょう。
木製のものを使えば湿気を吸収し、同時に履きジワを伸ばして革の形を整えてくれます。一日履いた靴は想像以上に水分を含んでいるため、そのまま放置するとカビや型崩れの原因になります。履いた直後に入れることが、一番効果的です。
③:汚れが気になる場合 ― クロスで軽く拭き取り
雨に濡れたり、目に見える泥汚れが付いた日には、乾いたクロスで軽く拭き取ってからシューツリーを入れるのがおすすめです。
放置するとシミや硬化につながるため、応急処置的に汚れを落としておくだけで後の本格ケアが格段に楽になります。
④:翌日 ― 1日休ませて乾燥・調整(連日履きは“非推奨”)
靴は続けて履かずに、最低でも丸一日休ませましょう。内部の湿気が抜け、革本来のコンディションが回復します。2足以上をローテーションして履くことが、結果的に靴を長く使う最大の秘訣です。翌日の朝にはシューツリーを外し、通気の良い場所に並べておくだけで準備完了です。
「月に1〜2回」のスペシャルケア!
毎日のブラッシングやシューツリーでのケアに加えて、月に1〜2回はもう一歩踏み込んだメンテナンスを行うことで、革靴の美しさと耐久性が格段に高まります。
これは「栄養補給」と「艶出し」を目的とした、定期的なお手入れです。靴の状態をリセットしてあげることで、日常のケアだけでは補いきれない革の乾燥や色落ちを防ぎ、深い光沢を育てていきます。
①:リムーバーで古いワックスを除去
まず行うべきは「リムーバー」を使った汚れ落としです。
毎日のブラッシングでは落としきれない古いクリームや汗、油汚れは少しずつ革に蓄積していきます。これを放置すると表面が曇ったり、通気性が失われる原因に。専用のリムーバーやクリーナーをクロスに取り、靴全体をやさしく拭き上げることで革を素の状態に戻し、後のクリームがしっかり浸透しやすくなります。
靴クリームで栄養と補色
リムーバーでリセットしたら「靴クリーム」の出番です。
乳化性クリームをクロスで薄く伸ばし、全体に栄養と油分・水分を与えます。特に色付きクリームを使うと、擦れた部分の小さな色落ちを補い、均一で美しい仕上がりが得られます。
定期的な栄養補給を怠ると、革は乾燥してシワやひび割れを起こしやすくなるため、月単位での補給が欠かせません。
③:豚毛ブラシとクロスで艶出し仕上げ
クリームを塗布したあとは「豚毛ブラシ」で刷り込み、全体になじませながら余分な成分を落とします。
この段階で軽く熱を帯びた摩擦が生まれ、自然な光沢が引き出されます。最後にクロスで軽く磨き上げれば、しっとりとした艶のある仕上がりに。
これが革靴本来の美しさを引き出す仕上げでとなります。
④:ワックスで「鏡面磨き」
より一層の美しさを求めるなら、「ワックス(靴蝋)」による鏡面磨きをおすすめします。
専用のワックスを少量ずつ薄く重ねて塗り、専用の布で円を描くように磨き込むことで、表面に強い光沢と耐水性の膜を作ります。
鏡面のようなピカピカの仕上がりは高級感が増すだけでなく、雨や汚れから革を守る防護効果も高めます。鏡面磨きは手間がかかりますが、靴の見た目を格段に引き上げるので、特別な日や気分を変えたいときに行うと効果的です!
まとめ:正しいメンテナンスで革靴を長持ちさせよう
本記事では革靴のメンテナンス方法について詳しく解説してきました。
まず覚えておいていただきたいことは、定期的なスペシャルケアももちろん大切ですが、実は1日数分の汚れ落としも大切だということ。
当社スピカでは革靴のオーダーメイド製作はもちろん、購入後のメンテナンス方法の共有から、メンテナンスアイテムの販売まで、専門的な知見を踏まえてご提案いたします。
初めて革靴に挑戦する方のサポートもいたしますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います!