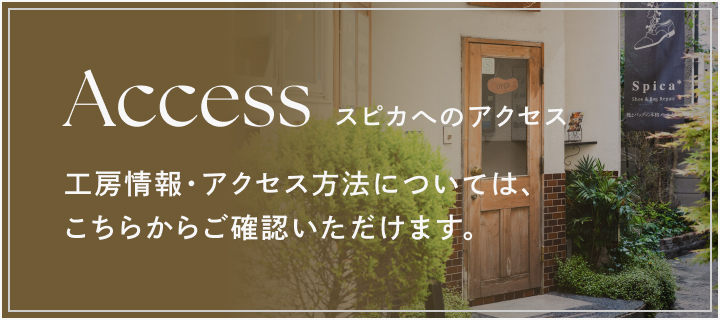下駄箱にしまった革靴、翌シーズンに取り出してみたらカビだらけ。
実は、こんな経験をした人は少なくありません。
調査によると、収納スペースの湿気やカビに不安を感じる人が96.3%にも上り、約32%が革製品のカビを特に懸念しています。
革靴の保管で大切なのは、「日常的に履く靴」と「シーズンオフの靴」で方法を使い分けることです。
履いた後すぐにブラッシングして乾燥させるだけで十分な日常保管と、徹底的にクリーニングして栄養を与える長期保管では、やるべきことがまったく違います。
- 革靴保管の基本3原則とNG例
- 日常保管の方法(履いた後のケア・シューキーパー・保管場所)
- 長期保管の方法(準備・カビ対策・季節別の注意点)
- トラブル発生時の応急処置
この記事を執筆しているスピカは、東京・元麻布で15年以上、1,000足以上のオーダーメイド靴を製作し、数千件の修理・メンテナンスに対応してきました。
その経験から得た知見をもとに、あなたの革靴を長く愛用するための保管方法をお伝えします。
革靴の保管、何を守れば失敗しない?

革靴の保管には、シチュエーションに関わらず共通する「基本原則」があります。まずはこの基本を押さえることで、カビや型崩れのリスクを大きく下げられます。
湿度管理・形状保持・定期ケアの3原則
湿度管理(カビを防ぐ)
革靴にとって湿気は最大の天敵です。カビの胞子は湿度60%以上、温度20~30℃の環境で急速に増殖し、革の表面だけでなく内部まで侵食します。
一度カビが革の繊維に入り込むと完全に除去することは困難で、革が変色したり強度が低下したりします。
湿度の高い梅雨時はシューズボックス内に除湿剤を置き、扉や蓋を時々開けて湿気を逃がす習慣をつけましょう。収納場所に除湿剤を入れ、定期的に換気することが、カビを防ぐための基本的な対策です。
形状保持(型崩れを防ぐ)
革靴は履くと内部の湿気と足圧で形が歪み、甲の曲がる部分を中心に深いシワができます。そのまま乾燥するとシワが定着し、革がひび割れる恐れがあります。
革は一度深く折り曲げられた状態で乾燥すると、その形状が固定されてしまいます。シワの部分は革が繰り返し屈曲するため、繊維が損傷しやすく、そこからひび割れが進行します。
特にひび割れは修復が難しく、靴の寿命を大きく縮める原因となります。帰宅後すぐに木製シューキーパーを入れて靴本来の形に整えることが、型崩れを防ぐ基本です。
定期ケア(状態を維持する)
一度しまった革靴も、月に1回は外に出してメンテナンスし、状態をチェックすることが大切です。
革靴を保管している間も、季節や天候によって湿度や温度は常に変化しています。夏には湿気でカビが発生し、冬には乾燥で革がひび割れることがあります。
これらの変化に気づかず放置すると、取り返しのつかないダメージになってしまいます。定期的に外に出して陰干しで風を通すことで、カビの予防にもなります。乾燥していればクリームを塗るなど早めに対処しましょう。
これだけは避けたい!保管のNG例3つ
正しい方法を知る前に、「やってはいけないこと」を押さえておくと失敗を避けられます。
NG1:濡れた靴をすぐ密閉収納すること
雨で靴が濡れた直後、そのまま下駄箱に入れるのは厳禁です。
密閉された下駄箱の中では湿度が急上昇し、24時間以内にカビの胞子が発芽し始めることもあります。濡れた靴から発生した湿気は下駄箱全体に広がり、他の靴にもカビが移る危険性があります。濡れた靴は必ず十分に乾燥させてから収納しましょう。
NG2:通気性のない箱に入れっぱなしにすること
新品を買って紙箱に入れたまま長期保管するのは良くありません。
紙箱は通気性が低く、湿気がこもって革が劣化する原因になります。特にビニール袋は通気性がゼロで、内部に湿気が閉じ込められてカビが発生しやすくなります。必ず通気性のある布製の袋や、穴を開けた紙箱を使用してください。
NG3:靴を詰め込み過ぎて収納すること
靴同士が接触するほど狭いスペースに押し込むと、通気性がさらに悪化しカビ増殖の温床になります。
靴と靴の間に空気の流れがなくなると、湿気が溜まりやすくなります。また、革同士が接触すると色移りや摩耗が起きることもあります。靴同士は最低でも5cm程度の間隔を空けて収納しましょう。
なぜ革は湿気と乾燥に弱いの?
革の特性を理解することで、保管方法の「なぜ」が腹落ちする知識をお伝えします。

革の構造が湿気と乾燥に弱い理由
革は動物の皮膚を加工したもので、コラーゲン繊維が複雑に絡み合った構造をしています。人間の肌と同じように、水分と油分のバランスが大切です。
湿気を吸収すると繊維が膨張し型崩れの原因となり、カビは革のコラーゲンを栄養源として成長するため革自体がダメージを受けます。
逆に乾燥すると繊維が硬化し柔軟性を失い、ひび割れが発生します。
革にとって最適な湿度は40~50%程度で、湿度60%を超えるとカビのリスクが高まり、湿度30%を下回ると乾燥による劣化が進みます。
型崩れが起こる仕組みとシューキーパーの役割
革には「可塑性」があります。これは、力が加わると形が変わり、その変わった形を維持する性質のことです。この性質により、革靴は足に馴染んでいきますが、同時に型崩れの原因にもなります。
靴を履くと足の形に沿って革が曲がりシワができ、この状態で乾燥するとシワが固定され、最終的にひび割れてしまいます。
シューキーパーを入れることで、靴を本来の形に戻し、シワを伸ばして悪い形での固定を防ぎます。木製シューキーパーは吸湿性もあり、湿気を取りながら形を整えてくれます。
スエード・エナメル・コードバンの保管
革の種類によって、保管方法も少し変わります。
スエード(起毛革)
スエードは起毛した繊維の隙間に埃や汚れが入り込みやすく、これが湿気と結びつくとカビの原因になります。水や汚れに弱いため、保管前には特に注意が必要です。
保管前に専用ブラシでブラッシングし、履きジワや縫い目の部分は念入りに汚れを落としましょう。防水スプレーを使用すると汚れや湿気から保護できます。
繊維が立っている構造のため通常の革よりも表面積が大きく、湿気を吸収しやすい特性があります。起毛革は水分を含むと繊維が寝てしまい、質感が損なわれるだけでなくシミになりやすいため、除湿剤を多めに配置して慎重な湿度管理が必要です。
エナメル(パテントレザー)
エナメルは表面の樹脂コーティングが高温で軟化し、ベタつきやひび割れが発生する可能性があります。夏場の保管には特に注意してください。
特に30℃を超える環境では樹脂が変質しやすく、一度ベタついたり変形すると元に戻りません。高温環境では樹脂が溶け出して、接触した靴に色移りや樹脂の転写が起こることがあります。
エナメル同士が接触すると、互いにくっついてしまうこともあるため、他の革靴と接触させず、必ず個別に保管しましょう。保管場所は直射日光が当たらず、温度変化の少ない涼しい場所を選んでください。
コードバン(馬革)
コードバンは馬の臀部の皮下にある緻密な層を使用した高級素材で、水に弱く、水濡れすると水ぶくれやシミができやすくなります。
牛革よりも繊維が詰まっているため、水分が浸透すると膨張して水ぶくれを起こします。乾燥にも弱く、ひび割れしやすいため、保革クリームでのケアが重要です。
通常の牛革よりもデリケートなため、より丁寧なケアが必要となります。湿度40~50%の環境を維持し、急激な温度変化も避けてください。非常に高価な素材のため、少しでも異変を感じたら早めにプロに相談することをお勧めします。
日常的に履く革靴は、どう保管すればいい?
「履いた後に何をすべきか」「普段使いの革靴をどこにどう収納するか」を知ることで、靴の寿命は大きく延びます。

履いた後すぐにやるべきこと
帰宅後すぐに馬毛ブラシで軽くブラッシングし、表面の埃や汚れを落としましょう。汚れを放置するとカビや雑菌の温床になります。
次に、風通しの良い日陰で24時間以上陰干しして乾燥させます。人の足は1日にコップ1杯分もの汗をかくため、この湿気を逃がさないとカビやニオイの原因になります。直射日光や暖房器具の近くは避けてください。
次に木製シューキーパーを入れて靴本来の形に戻し、シワを伸ばします。木製シューキーパーは吸湿性があり、靴内部の湿度を調整する働きもあります。靴のサイズに合ったものを選びましょう。
下駄箱での保管方法
風通しが良く、直射日光が当たらない場所が理想です。
下駄箱は湿気がこもりやすいため、定期的に扉を開けて換気し、下駄箱内に除湿剤(シリカゲルや備長炭)を置きましょう。下駄箱の上段は湿気が少ないため、革靴を置くのに適しています。
靴を詰め込みすぎず、靴同士の間隔を空けることも大切です。紙箱は通気性が低いため、長期保管には向きません。使う場合は箱に穴を開けて通気性を確保し、乾燥剤を入れましょう。

初めての革靴、正しくメンテナンスできてる?革靴職人が手入れ方法を詳しく解説!
「革靴はメンテナンスが必須!」と聞くけど、いざ革靴を買ったら何から手をつけていいのかわからない…、という方も多いと思います。 そこで本記事では、具体的にどう革靴をメンテナンスしていけばいいのか?を革靴職人が徹底解説していきます! この記事を読めば、こんな悩みが解決します! そもそも「
シーズンオフの靴、どう保管すればカビない?
長期間しまい込む前に何をすべきか、数カ月後に出した時にカビや劣化していないか心配という不安に応えます。

長期保管前に絶対やるべき準備
長期保管前には、徹底的な準備が必要です。
まずブラッシングで表面の汚れを落とし、リムーバーで革の表面をクリーンにしましょう。履きジワや縫い目の部分は汚れが溜まりやすいため、念入りにブラッシングすることが大切です。内側も消臭スプレーや除菌スプレーを使用してください。
次に保革クリームで栄養を与えます。米粒大の量を布に取り、革全体に薄く均一に伸ばします。塗りすぎは逆にカビの原因になります。
クリームを塗った後は24時間以上陰干ししてから保管し、必ず木製シューキーパーを入れましょう。除湿剤(シリカゲルや備長炭)を靴1足につき1つ使用し、通気性のある布製の靴袋で保管します。保管場所は湿気の少ない高い位置(クローゼットの上段など)が理想です。
梅雨・夏・冬、季節ごとの注意点
梅雨時期(6月~7月)は湿度が80%を超えることも多く、カビのリスクが最大です。除湿機やエアコンの除湿機能をフル活用し、靴箱の扉を頻繁に開けて換気してください。
夏(8月~9月)は高温多湿で、直射日光が当たる場所は絶対に避けてください。革が変色・硬化します。
冬(12月~2月)は暖房による乾燥に注意が必要です。暖房器具の近くに置かず、月に1回程度保革クリームで栄養を補給しましょう。
春・秋(3月~5月、10月~11月)は比較的安定した気候で、保管には適した季節です。シーズンの変わり目はしっかりクリーニングと保革を行いましょう。
月に1回は靴を取り出して状態をチェックし、カビの有無、革の乾燥状態、除湿剤の状態を確認してください。
カビや型崩れ、見つけたらどうすればいい?
カビや型崩れは、革靴の寿命を大きく縮める原因になります。見つけたときにどう対処するかで、その後のコンディションが決まります。

自分でできる応急処置
軽度のカビ(白い粉状)の場合は、すぐに屋外で乾いた布やブラシでカビを拭き取ってください(室内で拭くとカビが飛散します)。
次に濃度70~80%のエタノールを染み込ませた布で、カビ部分を拭き、完全に乾燥させた後、保革クリームを塗ってください。
軽度の型崩れの場合は、霧吹きで軽く湿らせてからシューキーパーを入れ、数日間形を整えます。
軽度のひび割れの場合は、保革クリーム(デリケートクリームなど)を丁寧に塗り込んでください。
重度のカビ・型崩れ・ひび割れの場合は、革の内部まで侵食しており、プロに相談するのが安全です。
プロに任せるべき時
以下のような状態の場合は、自分で対処せず専門家に相談することをお勧めします。
重度のカビ(緑色・黒色)が発生している時は革の内部まで菌糸が侵入しており、表面を拭くだけでは完全に除去できません。
不適切な処理をすると、カビが広がったり、革の変色・劣化を引き起こすことがあります。
深いひび割れやシワが入っている時は革の繊維が断裂している状態で、無理にクリームを塗り込むと亀裂が広がる危険性があります。
型崩れがひどく、自分では元に戻せない時は構造的な変形が進んでいる場合は、専用の木型や道具を使った修復が必要です。
色褪せや変色が起きている時は革の染料が劣化している状態で、プロの染め直し技術でなければ元の色を再現できません。
大切な靴で失敗したくない場合、高価な靴や思い入れのある靴の場合は、早めに専門家に相談することで、修復可能な範囲が広がります。
スピカでは、15年以上の経験を持つ職人がカビの除去から型崩れの修正、ひび割れの補修、染め直しまで対応しています。
まずは写真を撮って、メールや問い合わせフォームで相談するのがお勧めです。
よくある質問|革靴の保管に関するQ&A

Q1: 革靴を保管する際、靴紐は外すべきですか?
A: 外す必要はありませんが、少し緩めることをお勧めします。
靴紐をきつく結んだまま保管すると、革に不要な圧力がかかり、型崩れの原因になることがあります。
長期保管の場合は、紐を少し緩めておくか、外して別に保管すると革への負担が減ります。靴紐自体も定期的に洗濯すると、清潔に保てます。
Q2: シューキーパーは靴を履いていない間、常に入れておくべきですか?
A: はい、できるだけ常に入れておくことをお勧めします。
シューキーパーは形状保持だけでなく、湿気を吸収する役割もあります。特に木製シューキーパーは、靴内部の余分な湿気を吸収し、革の劣化を防ぎます。
ただし、履いた直後の湿った状態で入れると、湿気が閉じ込められる可能性があるため、完全に乾燥してから(少なくとも24時間後)入れるのが理想です。日常的に履く靴であれば、帰宅後すぐに入れても問題ありません。
Q3: 下駄箱がカビ臭い場合、どう対処すればいいですか?
A: まず下駄箱内の靴をすべて取り出し、完全に換気してください。
次に、エタノール(濃度70~80%)を含ませた布で下駄箱の内部を拭き、カビの胞子を除去します。天板、側面、底面、すべての面を丁寧に拭きましょう。
完全に乾燥させた後、大容量の除湿剤や備長炭を複数配置し、定期的に扉を開けて換気する習慣をつけましょう。靴を詰め込みすぎず、靴同士の間隔を空けて通気性を確保することも重要です。
革靴を最高の相棒に育てよう
この記事では、革靴の保管方法について、日常保管と長期保管の2つの視点から解説してきました。
どちらも共通するのは、「湿度管理」「形状保持」「定期ケア」の3原則です。日常保管では履いた後のブラッシングとシューキーパーでの形状保持が基本で、長期保管では徹底的なクリーニングと栄養補給、カビ対策を徹底することが欠かせません。
この記事のポイント
- 湿度管理・形状保持・定期ケアの3原則を徹底する
- 日常保管と長期保管でやるべきことを使い分ける
- 木製シューキーパーで形状保持と湿度調整を行う
- 月1回の定期チェックでトラブルを早期発見する
正しい保管方法を実践すれば、革靴を10年、20年と履き続けられます。保管は「しまい込む」ことではなく、「休ませて育てる」ことです。
スピカは、東京・元麻布で15年以上、オーダーメイド靴の製造と革靴のメンテナンスに携わってきました。まずは今日から、履いた後のブラッシングを習慣にしてみましょう。困った時は、スピカへお気軽にご相談ください。